お子さんの将来を考えると、「大学に行かせてあげたい」と思うシングルマザーのみなさん、多いですよね。
でも「そもそも大学費用ってどれくらいかかるの?」「シングルマザーの私でも子どもを大学に行かせることができるの?」という不安や疑問をお持ちではありませんか?
実は、シングルマザー家庭でも利用できる様々な支援制度や奨学金が用意されているんです。
この記事では、シングルマザー家庭が活用できる大学費用の支援制度や奨学金、そして計画的に準備するためのポイントを詳しくご紹介します。
シングルマザーが直面する大学費用の課題

シングルマザーとして子育てをしていると、日々の生活費だけでも大変なのに、子どもの大学進学となると「本当にやっていけるのかな…」と不安になりますよね。
子どもには夢を追いかけてほしいけれど、現実の経済面を考えると躊躇してしまう…そんな気持ち、とてもよくわかります。
実際、大学4年間の総費用は、国公立で約500万円、私立文系で約800万円、私立理系だと約1,000万円近くかかると言われています。
これは決して小さな金額ではないですよね。でも、諦める前に知っておきたい支援制度や工夫があります。
ここではまず、シングルマザー家庭が大学費用について直面する具体的な課題を整理していきましょう。現状をしっかり把握することが、解決への第一歩です!
低収入による貯蓄の難しさ
シングルマザー家庭の多くが経験するのが、収入面での厳しさです。厚生労働省の調査によると、母子家庭の平均年間収入は約243万円と、全世帯平均の半分程度にとどまっています。
これは、「一人で稼ぎながら育児もこなす」という状況では、フルタイムで働くことが難しかったり、キャリアアップのための時間が取れなかったりするためでもあります。
日々の生活費や住居費、子どもの教育費(塾や習い事など)で精一杯で、大学進学のためにコツコツ貯金するのは現実的に難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
特に子どもが小さいうちは、保育料や習い事など出費がかさみがちです。また、突発的な出費(病気や家電の故障など)で、せっかく貯めた教育資金を崩さなければならないこともあるでしょう。
さらに、大学進学を考え始める高校生の頃には、受験費用や予備校代、さらには高校自体の費用(私立高校なら特に)もかかります。このような状況下で、大学の学費のための貯蓄を十分に確保できている家庭は少ないのが現実です。
「毎月少しずつでも貯めておけばよかった」と後悔する声も聞かれますが、そもそも貯蓄に回せる余裕がなかったという方がほとんどでしょう。
こうした経済的制約は、お子さんの進学先の選択肢を狭めてしまうことにもつながります。「行きたい大学があっても諦めなくてはいけないのか」「子どもの夢を支えられない」という不安や自責の念を抱えるシングルマザーの方も少なくありません。
しかし、経済的な理由だけで子どもの将来の可能性を制限する必要はないのです。この記事で紹介する様々な支援制度を上手に活用すれば、ひとり親家庭でも子どもの大学進学の夢を実現させることができます。
家計のやりくりと教育費の両立

毎月の生活費でカツカツなのに、大学資金なんて貯められるわけないよね…

その気持ち、すごくわかる!でも、少額からでも始められる方法や支援制度があるから、一緒に考えていきましょう!
限られた収入の中で家計をやりくりしながら、大学資金を貯めていくのは本当に大変です。多くのシングルマザーが「今月の生活費を確保するので精一杯」という状況を経験します。
しかし、経済的に厳しい状況でも工夫次第で少しずつ準備を進めることは可能です。例えば、児童扶養手当や児童手当の一部を教育費として積み立てる方法や、年に数回ある臨時収入(税金の還付金やボーナスなど)を教育資金に回すなどの工夫をしている方もいます。
また、子どもが中高生になったら、奨学金や支援制度についての情報を集め始めるなど、お金以外の「準備」を進めておくことも大切です。無理なく続けられる方法を見つけて、小さな一歩から始めていきましょう。
奨学金や教育ローン審査のハードル
大学進学を考える際、多くの家庭が頼りにするのが奨学金や教育ローンです。しかし、シングルマザー家庭ではこれらの利用にも独自の課題があります。
まず、貸与型奨学金(返済が必要なタイプ)は、将来的な返済能力が審査されます。シングルマザー家庭は収入が限られていることが多く、特に子どもが複数いる場合は、返済の見通しが立ちにくいと判断されることもあります。
また、教育ローンについては、一般的に安定した収入や保証人が求められることが多いです。特に民間の教育ローンでは、年収や雇用形態(正社員かパートか)などが重視され、非正規雇用の割合が高いシングルマザー家庭では審査に通りにくいケースがあります。
さらに、過去にクレジットカードの支払い遅延などの金融トラブルがあると、それが理由で審査に通らない可能性も高まります。
保証人についても大きな課題です。教育ローンによっては保証人を立てる必要がありますが、離婚後は元配偶者に頼れないケースが多く、頼れる親族もいない場合は選択肢が限られてしまいます。特に年齢制限がある教育ローンでは、祖父母の年齢が上限を超えていると保証人になれないこともあります。
こうした状況から、「奨学金は借りられるかわからない」「教育ローンの審査に通るか不安」といった懸念を抱えているシングルマザーは少なくありません。
しかし、近年はひとり親家庭向けの特別枠を設けている奨学金制度や、審査基準を緩和した教育ローンなども増えています。
また、保証会社を利用することで保証人不要の制度も広がってきました。各制度の特徴や申込条件をよく調べ、自分の状況に合ったものを選ぶことが大切です。
- 収入の少なさから返済能力を懸念される
- 非正規雇用だと審査が厳しくなる
- 保証人を立てることが難しい
- 複数の子どもがいる場合の返済負担が大きい
シングルマザー向けの特別枠と申請方法
奨学金や教育ローンの申請において、シングルマザー家庭は「ひとり親家庭」として特別な配慮を受けられるケースがあります。
例えば、日本学生支援機構の奨学金では、一人親世帯の場合、通常より収入基準が緩和されることがあります。また、母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭専用の支援制度として、教育資金の貸付を行っています。
こうした特別枠を利用するためには、「児童扶養手当証書」や「ひとり親家庭等医療費助成受給者証」などの証明書が必要になることが多いので、事前に準備しておきましょう。
また、申請時期も重要です。多くの奨学金は高校3年生の春から夏にかけて申請が始まりますが、中には高校2年生のうちから準備が必要なものもあります。
早めに情報収集を始め、学校の先生や自治体の窓口に相談しながら、計画的に申請手続きを進めていくことが成功のカギとなります。
学費負担と自身の老後資金の両立
シングルマザーにとって、子どもの大学教育費と自分自身の老後資金の確保は、両方とも避けて通れない重要な課題です。
特に40代、50代のシングルマザーの方々は、子どもの大学進学時期と自分の老後準備が重なる時期にあり、「子どもの教育にお金をかけるべきか、自分の老後に備えるべきか」という難しい選択に直面することになります。
多くのシングルマザーが「子どものためなら自分が我慢するのは当たり前」という思いから、老後資金よりも子どもの教育費を優先させがちです。
しかし、長期的な視点で見ると、親の老後が経済的に不安定になれば、結果的に子どもに負担がかかる可能性もあります。将来子どもが就職した後に、親の生活費の援助をする必要が出てくるかもしれないのです。
また、子どもの教育のために貯金を全て使い切ったり、多額の教育ローンを組んだりすることで、退職後の生活が厳しくなるリスクもあります。
教育ローンの返済期間が長期にわたる場合、退職後の年金収入だけでは返済が難しくなることも考えられます。
特に、シングルマザーの場合は配偶者からの年金分割があるとはいえ、一般的に年金額が少なくなる傾向があり、老後の経済的不安は大きいものです。
このように、子どもの教育費と自分の老後資金の両立は、シングルマザーにとって非常に悩ましい問題です。
しかし、「どちらかを犠牲にする」という二者択一の考え方ではなく、両方をバランスよく確保するための方法を考えることが大切です。
例えば、子どもには給付型奨学金や授業料免除制度などの支援を最大限活用してもらい、親は無理のない範囲で教育費を負担しながら、少額でも老後資金を積み立てていくという方法があります。
- 子どもに活用できる支援制度を徹底的に調査する
- 老後資金は少額からでも積立を始める
- 無理のない範囲で教育費を負担する計画を立てる
- 将来的な家計の見通しを子どもと共有する
将来の家計を考えた教育投資

子どもの大学費用のために貯金を全部使ったら、私の老後はどうなるの…?

そのジレンマ、多くのママが抱えているわ。でも両方大切にする方法を一緒に考えましょう!
教育費と老後資金、どちらも大切な資金計画ですが、バランスを取りながら考えることが重要です。まず、子どもの大学進学については、全額を親が負担するのではなく、子ども自身も一部を担う方法を検討してみましょう。
例えば、大学在学中のアルバイト収入で生活費の一部を賄ったり、貸与型奨学金の一部を将来子ども自身が返済する計画を立てたりする方法があります。
また、親としては、「いくらまでなら出せるか」という限度額を設定し、その範囲内で進学先を考えることも大切です。
老後資金については、iDeCoやつみたてNISAなど税制優遇のある制度を活用して、少額からでも積立を始めることがおすすめです。
子どもの将来と自分の将来、どちらも大切にするバランス感覚を持つことが、長期的に見た家族全体の幸せにつながります。
情報不足による支援制度の未活用
シングルマザー家庭が直面する大きな課題の一つに、支援制度に関する情報不足があります。
実は、日本には様々な教育支援制度があり、特にシングルマザーを含むひとり親家庭を対象とした特別な支援も数多く存在します。
しかし、これらの情報が十分に届いていないために、活用できるはずの制度を利用できていないケースが非常に多いのです。
例えば、2020年4月から始まった「高等教育の修学支援新制度」では、一定の条件を満たす低所得世帯の学生に対して、授業料・入学金の減免と給付型奨学金の支給が行われています。
この制度を利用すれば、国公立大学ならほぼ無償、私立大学でも大幅な負担軽減が可能になるケースもあります。
特にひとり親世帯は所得基準で有利になることが多いのですが、この制度の詳細を知らないために申請していないシングルマザー家庭も少なくありません。
また、各自治体が独自に実施している奨学金制度や、民間団体が提供する給付型奨学金、大学独自の授業料減免制度など、様々な支援の選択肢があります。
特に地方自治体の奨学金は、その地域出身者や在住者を対象としているため競争率が比較的低く、利用しやすいケースもあります。
しかし、これらの情報はあまり広く知られておらず、自ら積極的に調べない限り見つけることが難しいのが現状です。
情報不足に陥りやすい理由としては、子育てと仕事の両立で精一杯のシングルマザーが情報収集に割く時間的余裕がないことや、どこに相談すれば良いのかわからないという問題があります。
また、支援制度は年々変更されることも多く、最新情報をキャッチアップするのも容易ではありません。こうした状況から、「どうせうちは支援を受けられないだろう」とあきらめてしまうケースも少なくないのです。
支援情報の収集方法とコツ
支援制度に関する情報を効率よく集めるためには、いくつかの方法があります。まず、子どもが通う高校の進路指導の先生に相談することが最も直接的です。
学校には様々な奨学金の案内が届いているため、子どもの成績や家庭状況に応じたアドバイスをもらえることが多いです。また、お住まいの自治体の教育委員会や福祉課にも相談してみましょう。
自治体独自の支援制度を紹介してもらえることがあります。さらに、「ひとり親支援センター」や「母子家庭等就業・自立支援センター」といった専門の相談窓口も心強い味方です。
これらの窓口では、教育費だけでなく生活全般の支援についても相談に乗ってくれます。インターネットでは、「ひとり親 大学 奨学金」「シングルマザー 進学支援」などのキーワードで検索すると、様々な情報が見つかります。
特に日本学生支援機構(JASSO)のウェブサイトでは、奨学金に関する詳細な情報が得られます。子どもが進学を考え始める中学生の頃から、少しずつ情報を集め始めることで、選択肢を広げることができるでしょう。
高等教育の修学支援新制度を活用しよう

2020年4月からスタートした「高等教育の修学支援新制度」は、シングルマザー家庭にとって大きな味方となる可能性がある支援制度です。
この制度は、低所得世帯の学生を対象に、授業料・入学金の減免と返還不要の給付型奨学金の支給を組み合わせた手厚い支援を行うもの。
特に、ひとり親家庭は世帯収入の面で採用されやすい傾向があります。「大学なんて無理」とあきらめる前に、ぜひこの制度について知っておきましょう。
対象となる大学や専門学校も年々増えていて、活用の幅も広がっています。この制度をうまく利用すれば、家計への負担を大幅に減らしながら、子どもの進学の夢を実現することができるかもしれません。
授業料・入学金の免除や減額の内容
高等教育の修学支援新制度における授業料・入学金の免除や減額は、シングルマザー家庭の大きな助けとなる可能性があります。
この制度では、家計の状況に応じて支援額が3段階に分かれており、最も支援が厚い「第Ⅰ区分」では授業料と入学金が全額免除となります。
具体的には、国公立大学の場合、年間約54万円の授業料と約28万円の入学金が免除されるため、実質的に学費が無料に近い状態で大学に通うことができます。
私立大学の場合は、国公立大学の授業料を上限として減免されるため、全額免除にはなりませんが、それでも大きな負担軽減になります。
例えば、年間授業料が100万円の私立大学の場合、第Ⅰ区分なら約54万円が免除され、実質的な負担は約46万円になります。入学金についても同様に、国公立大学の入学金を上限として免除されます。
「第Ⅱ区分」では授業料と入学金の3分の2が、「第Ⅲ区分」では3分の1が免除されます。どの区分に該当するかは世帯の所得によって決まりますが、特にシングルマザー家庭を含むひとり親世帯については、通常の世帯より優遇されている点が大きなポイントです。
例えば、母子家庭で子ども1人(大学生)の場合、母親の年収が約270万円以下なら第Ⅰ区分、約300万円以下なら第Ⅱ区分、約330万円以下なら第Ⅲ区分に該当する可能性が高いです(これらは目安であり、詳細な条件は日本学生支援機構のウェブサイトで確認してください)。
さらに重要なのは、この免除・減額は入学前に申請して認定を受ける必要があるという点です。多くの場合、高校3年生の時点で申請手続きを行います。
学校の先生や進路指導の担当者に早めに相談して、必要な書類や申請のタイミングを確認しておくことが大切です。また、一度認定を受けても、毎年継続のための審査があるため、大学入学後も継続的な手続きが必要になります。
ただし、認定条件を満たしていれば、基本的に4年間(医学部などは6年間)継続して支援を受けることができます。
- 第Ⅰ区分:授業料と入学金の全額免除(国公立大学の場合、年間約82万円軽減)
- 第Ⅱ区分:授業料と入学金の3分の2免除(国公立大学の場合、年間約55万円軽減)
- 第Ⅲ区分:授業料と入学金の3分の1免除(国公立大学の場合、年間約27万円軽減)
実質無償化の可能性と条件

うちの収入で本当に大学が無償になるの?信じられないんだけど…

条件さえ合えば本当に可能なのよ!特にシングルマザー家庭は優遇されるケースが多いわ!
高等教育の修学支援新制度を最大限活用すれば、特に国公立大学では実質的な無償化が実現する可能性があります。第Ⅰ区分に認定されると、授業料と入学金が全額免除されるだけでなく、後述する給付型奨学金も最大額が支給されます。
これにより、授業料や入学金だけでなく、教科書代や生活費の一部もカバーできるため、家庭の経済的負担は大幅に軽減されます。ただし、無償化の実現には一定の条件があります。
まず、支援対象となる大学や専門学校に進学することが必要です。全ての学校が対象ではないため、進学先選びの段階から確認が必要です。
また、学業成績も考慮されるため、高校時代の勉強も重要になります。具体的には「学習意欲があり、学業成績が一定の水準以上」という基準を満たす必要がありますが、こうした条件を満たせば、シングルマザー家庭の子どもでも経済的な心配をせずに大学進学を目指すことが可能になります。
給付型奨学金の支給額と条件
高等教育の修学支援新制度のもう一つの大きな柱が、返済不要の給付型奨学金です。この奨学金は、前述の授業料・入学金免除と併せて利用することで、より手厚い支援を受けることができます。
給付型奨学金の支給額は、世帯の所得(支援区分)、通学形態(自宅通学か自宅外通学か)、進学先(国公立か私立か)によって異なります。
例えば、第Ⅰ区分(最も支援が手厚い区分)の場合、国公立大学の自宅通学なら年間約35万円、自宅外通学なら年間約80万円の給付型奨学金が支給されます。
私立大学の場合はさらに金額が増え、自宅通学で年間約46万円、自宅外通学で年間約91万円となります。第Ⅱ区分では第Ⅰ区分の3分の2の金額が、第Ⅲ区分では3分の1の金額が支給されます。
この給付型奨学金の大きな特徴は、返済不要であることです。従来の奨学金は貸与型(借金)が中心でしたが、この制度では文字通り「給付」されるため、将来の返済負担を心配する必要がありません。
特にシングルマザー家庭の子どもにとって、将来の返済負担がないことは、卒業後のスタートを切る上で大きなメリットとなります。
給付型奨学金を受けるための条件としては、先ほど説明した授業料・入学金免除と同様に、世帯の所得が基準以下であることが必要です。
特にシングルマザー家庭を含むひとり親世帯は、通常の世帯より所得基準が緩和されているため、比較的受給しやすい傾向にあります。
また、学業成績については「学習意欲があり、学業成績が一定の水準以上」という基準があります。具体的には高校の評定平均値が3.5以上であることが望ましいとされていますが、3.5未満でも、所属高校等の推薦があれば対象となる可能性があります。
申請手続きは、授業料・入学金免除と同時に行います。多くの場合、高校3年生の時点で学校を通じて申請を行い、大学入学前に採用候補者として決定を受けます。
その後、実際に大学に入学した時点で正式に支給が始まります。給付型奨学金は原則として毎月振り込まれるため、定期的な生活費として活用することができます。
また、一度採用されると、適格認定(成績や出席率などの確認)に通れば、標準修業年限(4年間など)の間、継続して受給することができます。
- 国公立大学・自宅通学:約35万円
- 国公立大学・自宅外通学:約80万円
- 私立大学・自宅通学:約46万円
- 私立大学・自宅外通学:約91万円
返済不要の奨学金を最大限活用するコツ

返済不要の奨学金って本当にあるの?何か落とし穴とかない?

本当にあるわよ!ただし申請時期や条件をしっかり確認することが大切ね!
給付型奨学金を最大限活用するためには、いくつかのポイントがあります。まず最も重要なのは、申請時期を逃さないことです。
多くの場合、高校3年生の6〜7月頃から申請が始まりますが、学校によって異なる場合もあるため、早めに担任や進路指導の先生に確認しておきましょう。
また、申請に必要な書類(課税証明書や源泉徴収票、戸籍謄本など)の準備も計画的に進めておくことが大切です。
特にシングルマザー家庭の場合、ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当証書など)も必要になりますので、事前に確認しておきましょう。
さらに、この奨学金を受け続けるためには、大学入学後も一定の学業成績と出席率を維持する必要があります。
毎年行われる「適格認定」という審査に通らなければ、奨学金が停止されることもあるため、大学入学後も計画的な学習を心がけることが重要です。
このような点に注意しながら準備を進めれば、返済不要の給付型奨学金を最大限に活用し、大学生活の経済的基盤を作ることができるでしょう。
支援対象となる学校種と確認方法
高等教育の修学支援新制度を利用するためには、支援対象となる大学や専門学校に進学する必要があります。この制度の対象となるのは、国や自治体から「確認校」として認定された学校のみです。
すべての大学や専門学校が対象になるわけではないため、進学先を選ぶ際には必ず確認する必要があります。
支援対象となる学校種は、大学(国公立・私立)、短期大学(国公立・私立)、高等専門学校(4年生・5年生)、専門学校(専修学校専門課程)です。
多くの有名大学や一般的な国公立大学はほとんど対象になっていますが、一部の私立大学や専門学校は対象外の場合もあります。特に、経営状況や教育の質に問題があると判断された学校は対象から外れることがあります。
確認校かどうかを調べる方法としては、文部科学省や日本学生支援機構(JASSO)のウェブサイトで公開されている「確認校一覧」を確認するのが最も確実です。
また、各学校のホームページでも、「高等教育の修学支援新制度の対象校です」といった記載がある場合が多いです。オープンキャンパスや進学相談会などでも、直接学校の担当者に確認することができます。
重要なのは、志望校を決定する前にこの確認を行うことです。特に、経済的な支援が必要なシングルマザー家庭の場合、この制度を活用できるかどうかが大学選びの大きな判断材料になることもあります。
例えば、第一志望の大学が対象外で、第二志望の大学が対象校だった場合、経済的な面から進学先を再検討することも選択肢の一つです。
また、確認校であっても、学部や学科によっては対象外の場合もあります。特に、通信教育課程や夜間部、科目等履修生などは、制度の対象外となることがあるため、詳細を確認する必要があります。
進学を考えている学校が確認校かどうか不明な場合は、学校の学生課や入試課に直接問い合わせるのが最も確実です。
シングルマザー家庭にとって大きな経済的支援となる可能性があるこの制度を活用するためにも、進学先選びの段階からしっかりと情報収集をしておきましょう。
シングルマザーが利用できる奨学金や教育ローンの種類

高等教育の修学支援新制度以外にも、シングルマザー家庭が活用できる奨学金や教育ローンは様々あります。「うちの家庭は新制度の対象にならないかも…」と心配している方も、他の支援制度を組み合わせることで大学進学の道は開けます。
ここでは、日本学生支援機構の奨学金から自治体の支援制度、ひとり親家庭向けの特別な貸付制度まで、幅広い選択肢をご紹介します。それぞれの制度には特徴や申込条件がありますので、自分の状況に合ったものを選ぶことが大切です。
一つの制度だけでは足りなくても、複数の支援を組み合わせることで、より手厚いサポートを受けられる可能性があります。子どもの夢を応援するために、あらゆる選択肢を検討していきましょう!
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、大学生の経済支援として最も一般的で広く利用されている制度です。この奨学金には大きく分けて「給付型」と「貸与型」の2種類があります。
前述した高等教育の修学支援新制度における給付型奨学金もJASSOが運営していますが、それとは別に貸与型の奨学金も提供しています。
貸与型奨学金には「第一種奨学金(無利子)」と「第二種奨学金(有利子)」があります。第一種奨学金は利息がかからない分、第二種よりも審査が厳しく、学力基準や家計基準が設けられています。
国公立大学の場合、自宅通学で月額2万円〜5.4万円、自宅外通学で月額2万円〜6.4万円の範囲で選択できます(私立大学も同様の金額帯)。
一方、第二種奨学金は比較的審査が緩やかで、より多くの学生が利用しています。貸与月額は2万円から12万円までの間で、1万円単位で選択することができます。
シングルマザー家庭の場合、特に注目したいのが「特別控除」という制度です。JASSOの奨学金審査では、ひとり親家庭については一定額(2023年度は99万円)を収入から差し引いて計算するため、通常の家庭より有利に審査されることが多いです。つまり、同じ収入であれば、シングルマザー家庭の方が奨学金を受けやすくなっています。
また、返還時の負担を軽減する制度として、「所得連動返還型奨学金制度」もあります。これは、卒業後の収入に応じて毎月の返還額が変わる制度で、収入が少ない時期は返還額も少なくなります。
さらに、「返還期限猶予制度」や「返還免除制度」もあり、病気や失業などで返還が困難になった場合や、特定の職業(教員や医師など)に就いた場合に、返還が猶予または免除されることもあります。
JASSOの奨学金の申込みは、基本的に高校3年生の時に学校を通じて行います。申請時期は毎年春頃(4月〜6月)ですが、学校によって異なる場合もあるため、早めに担任や進路指導の先生に確認しておくことをおすすめします。
シングルマザー家庭の場合、提出書類として「児童扶養手当証書」や「戸籍謄本」なども必要になることが多いので、事前に準備しておくと安心です。
- 第一種奨学金:無利子、月額2万円〜6.4万円(学校種・通学形態により異なる)
- 第二種奨学金:有利子(上限3%)、月額2万円〜12万円から選択可
- 給付型奨学金:返済不要、世帯収入や学校種により支給額が異なる
- 入学時特別増額貸与奨学金:入学時の一時金として10〜50万円を貸与
貸与型奨学金を利用する際の注意点

奨学金の返済、将来子どもに負担をかけることにならないかな…

心配はわかるけど、計画的に利用すれば大丈夫!返済負担を減らす方法も色々あるわ
貸与型奨学金を利用する際は、将来の返済負担について事前によく考えておくことが重要です。特に第二種奨学金(有利子)の場合、卒業後の返済総額は借りた金額より増えることになります。
例えば、月額8万円を4年間借りると、元金は384万円ですが、利息を含めると総返済額は400万円を超える可能性があります。
月々の返済額は1〜2万円程度が一般的ですが、これが10〜20年間続くことを考えると、将来の家計に大きな影響を与えかねません。
そのため、本当に必要な金額だけを借りる、可能な限り無利子の第一種を選ぶ、返済計画を事前にシミュレーションするなどの対策が大切です。
また、親子で話し合い、返済を誰がどのように負担するのかを事前に決めておくことも重要です。「在学中の生活費は奨学金でまかない、卒業後は子ども自身が返済する」「授業料は親が、生活費は子どもが負担する」など、明確な役割分担をしておくと、将来のトラブルを防げます。
さらに、繰上返済制度や返還期限猶予制度などの仕組みも理解しておくと、返済が難しくなった時の対処法が分かり、安心して利用することができるでしょう。
自治体が提供する学費支援制度
JASSOの奨学金に比べると知名度は低いものの、各自治体(都道府県や市区町村)が独自に提供している学費支援制度も、シングルマザー家庭にとって貴重な選択肢となります。
これらの制度は地域によって名称や内容が異なりますが、一般的に「地方公共団体奨学金」や「〇〇県(市)奨学金」などと呼ばれています。
自治体の奨学金の大きな特徴は、地元出身者や在住者を優先的に支援する点です。例えば、「〇〇県内の高校を卒業し、大学に進学する学生」や「〇〇市に住民票がある家庭の子ども」といった条件が設けられていることが多いです。
このため、JASSOの奨学金に比べて応募者が限定され、競争率が低くなる傾向があります。
支援内容も多様で、無利子または低金利の貸与型奨学金を提供している自治体が多いですが、中には返済不要の給付型奨学金を設けている地域もあります。
例えば、東京都では「東京都育英資金」として、月額2.5万円〜5.3万円の貸与型奨学金を提供しています。神奈川県の「神奈川県高等学校奨学金」、大阪府の「大阪府育成会奨学金」なども同様の制度です。
特にシングルマザー家庭にとって注目すべきは、ひとり親家庭を優先的に支援している自治体が多い点です。例えば、「ひとり親家庭優先枠」を設けていたり、選考基準においてひとり親家庭に加点があったりする制度も少なくありません。
また、所得基準も一般家庭より緩和されていることが多いため、比較的審査に通りやすい傾向があります。
自治体の奨学金情報を入手するには、お住まいの都道府県や市区町村の教育委員会のウェブサイトをチェックするのが最も確実です。
また、高校の進路指導室でも情報を得られることが多いです。申請時期は自治体によって異なりますが、多くは高校3年生の春から夏頃に募集が始まります。
中には高校2年生の時点で予約採用を行っている自治体もあるため、早めに情報収集を始めることをおすすめします。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の活用
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、ひとり親家庭を対象とした国の制度で、子どもの教育資金も含めた様々な資金を低利または無利子で貸し付ける制度です。
この制度はシングルマザー家庭にとって非常に心強い支援となります。特に、他の奨学金や教育ローンの審査に通らなかった場合でも、この制度なら利用できる可能性が高いという点が大きなメリットです。
教育に関連する貸付金としては、主に「修学資金」「就学支度資金」の2種類があります。修学資金は大学や短大、専門学校などの学費や生活費として利用でき、国公立大学の場合、月額6.7万円まで、私立大学の場合は月額7.9万円までの貸付が可能です。
就学支度資金は入学時に必要な資金として一時的に貸し付けられるもので、大学などの場合、59万円まで借りることができます。
この制度の大きな特徴は、低利または無利子で貸し付けが受けられることです。母子家庭の場合、連帯保証人を立てられれば無利子、連帯保証人がいなくても年利1.0%という低金利で利用できます(※金利は変更される可能性があるため、最新情報を確認してください)。
また、返済期間も比較的長く設定されており、修学資金の場合は卒業後6か月経過してから10年以内、就学支度資金は5年以内となっています。
申請は、お住まいの都道府県・市区町村の福祉事務所や母子・父子自立支援員に相談することから始まります。
必要書類としては、「児童扶養手当証書」や「戸籍謄本」「住民票」「所得証明書」などが一般的ですが、自治体によって若干異なる場合があります。申請時期に特に制限はありませんが、入学前に申請手続きを済ませておくことが望ましいでしょう。
国の教育ローン(教育一般貸付)の特徴
国の教育ローン(教育一般貸付)は、日本政策金融公庫が提供する教育専用の低金利融資制度です。民間の教育ローンと比較して、金利が低く設定されている点が最大の特徴で、シングルマザー家庭にとっても利用価値の高い選択肢の一つです。
国の教育ローンでは、学生一人につき最大450万円まで(一部の場合は550万円)の融資を受けることができます。
金利は固定金利で、2023年時点では年1.95%程度となっています(※金利は変動する可能性があるため、最新情報を確認してください)。返済期間は最長15年以内で、元金の据置期間を設けることも可能です。
このローンの利用目的は幅広く、入学金、授業料などの学校納付金はもちろん、教科書代、パソコン購入費、下宿代など、教育に関連するほとんどの費用に充てることができます。
また、入学前から卒業までの間、必要に応じて随時利用申込みが可能なため、計画的に資金を確保することができます。
シングルマザー家庭にとって特に注目すべき点は、「ひとり親家庭特例」が設けられていることです。通常、国の教育ローンを利用するためには世帯の年収に上限(例:世帯年収790万円以内など)がありますが、ひとり親家庭の場合はこの基準が緩和され、より利用しやすくなっています。
また、ひとり親家庭を含む「母子家庭または父子家庭」「世帯年収200万円以内」「子ども3人以上の世帯」などの条件に該当する場合は、金利の引き下げ措置(年0.45%の引き下げ)が適用されることもあります。
申込み方法は、インターネット、郵送、窓口の3つがあり、必要書類としては申込書のほか、住民票、源泉徴収票または確定申告書の写し、合格通知書または在学証明書などが一般的です。
ひとり親家庭であることを証明するために、「児童扶養手当証書」や「戸籍謄本」なども求められます。審査期間は約2週間〜1か月程度かかるため、進学が決まったら早めに申込みを検討するとよいでしょう。
民間教育ローンとの比較ポイント
教育資金の調達を検討する際、国の教育ローンと民間金融機関の教育ローンのどちらを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。両者を比較する主なポイントとしては、まず金利の違いがあります。
一般的に、国の教育ローンは民間より低金利(年1.95%程度)で提供されていることが多いです。特にひとり親家庭への優遇措置があるため、さらに低い金利(年1.5%程度)で利用できる場合もあります。
一方、民間の教育ローンは金利が若干高め(年2〜4%程度)ですが、審査のスピードが速く、最短で翌日には融資が受けられるケースもあります。
申込条件も異なり、国の教育ローンには世帯年収の上限がありますが、民間ではそうした制限がない代わりに、信用情報や雇用形態がより重視される傾向があります。
このため、非正規雇用のシングルマザーの場合、民間の審査は厳しくなることもあります。また、融資上限額も、国の教育ローンは学生一人あたり最大450万円までですが、民間では1,000万円以上の融資も可能な場合があります。
返済期間についても違いがあり、国の教育ローンは最長15年、民間では最長20年程度のケースもあります。総合的に見ると、シングルマザー家庭の場合は、金利の低さや審査基準の優遇を考慮すると、国の教育ローンの方が利用しやすい傾向があると言えるでしょう。
シングルマザーが子どもと一緒に考える大学進学プラン

大学進学は、親だけでなく子ども自身にとっても人生の大きな分岐点です。特にシングルマザー家庭では、経済的な面から親子で協力して進学プランを考えることが重要になります。
「お金の話を子どもにするのは気が引ける…」という気持ちもわかりますが、実際の家計状況を踏まえた現実的な話し合いが、子どもの将来のためにも必要です。
ここでは、親子で一緒に大学進学について考えるためのポイントを紹介します。オープンな対話を通じて、子どもの夢を応援しながらも、無理のない進学プランを作っていきましょう。
子どもを信頼し、一緒に考えるプロセスそのものが、子どもの成長にとって貴重な経験となるはずです。
学費全体の把握と情報共有の重要性
大学進学を考える際、まず押さえておきたいのは「実際にどれくらいの費用がかかるのか」という全体像です。
大学の学費は、入学金、授業料、施設設備費などの「学校納付金」と、教科書代、通学費、生活費などの「その他の費用」に大きく分けられます。これらを合わせた総額を把握しておくことが、進学プランを立てる第一歩となります。
学校納付金は大学の種類や学部によって大きく異なります。一般的に、国公立大学の場合、4年間でおよそ250万円〜300万円程度、私立大学の文系学部なら400万円〜600万円程度、私立大学の理系・医歯薬系学部になると600万円〜1,000万円以上かかることもあります。
これに加えて、自宅外通学の場合は、アパート代や光熱費などの生活費として月額8万円〜12万円程度が必要になるでしょう。
こうした費用の全体像を子どもと共有することは、非常に重要です。シングルマザー家庭の場合、経済的な制約があることを子どもに正直に伝え、その中でどのような選択肢があるのかを一緒に考えることが大切です。
「どんな大学でも行かせてあげたい」という気持ちから財政状況を隠してしまうと、後になって「やっぱり無理だった」ということになりかねません。
情報共有の方法としては、例えば「教育資金の家計簿」のようなものを作成し、現在の貯蓄額、今後貯められる見込み額、利用可能な奨学金や教育ローンの額、そして大学4年間でかかる総額を書き出してみるとよいでしょう。そうすることで、どの程度の資金が不足するのか、または余裕があるのかが具体的に見えてきます。
また、子どもの希望する進路(大学・学部・地域など)によって必要な費用が変わってくることも伝えておくことが大切です。
例えば、地元の国公立大学に進学するのと、遠方の私立大学に進学するのとでは、4年間の総額に数百万円の差が出ることもあります。こうした情報を子どもと共有することで、現実的な進学先の選択肢を一緒に考えることができるようになります。
- 大学の種類別の学費相場(国公立・私立、文系・理系など)
- 生活費の目安(自宅通学・自宅外通学)
- 現在の家庭の貯蓄状況と今後の見通し
- 利用可能な奨学金や教育ローンの種類と金額
- 大学卒業後の返済計画
家計の現状を子どもと共有する方法

子どもに家計の話をすると、心配をかけたり、夢を諦めさせてしまうかも…

でも、オープンに話し合うことで、子どもは現実を理解し、自分なりの解決策を考えるきっかけになるわよ!
家計の現状を子どもと共有する際は、単に「お金がない」と伝えるのではなく、具体的な数字と可能性を示すことが重要です。
例えば、「今の貯蓄は〇〇万円あるけど、大学4年間でトータル△△万円かかるから、あと□□万円必要。でも奨学金を使えば月に××万円の援助が得られるし、ママも月に■■万円ずつ貯められる。だから一緒に計画を立てていこう」というように、前向きな姿勢で話し合いましょう。
また、話す時期も重要です。高校入学時や高校2年生の早い段階から少しずつ話題にしておくと、子どもも心の準備ができます。突然「実は大学費用が足りない」と言われるよりも、早めに状況を知らせて一緒に対策を考える時間を持つことで、子どもも自分の進路について主体的に考えるようになります。
大切なのは、経済的な制約があっても「何とかしよう」という前向きな姿勢を子どもに示すことです。また、子どもの意見や気持ちに耳を傾け、一方的に「これは無理」と決めつけないようにしましょう。一緒に情報を集め、様々な可能性を探ることで、親子の絆も深まり、子どもの自立心も育まれます。
利用可能な制度や奨学金の調査と準備
大学進学に向けて子どもと情報共有した後は、具体的にどのような支援制度や奨学金が利用できるのかを調査し、計画的に準備していくことが大切です。
シングルマザー家庭の場合、前述したように様々な支援制度が利用できる可能性がありますが、それぞれに申請時期や必要書類が異なります。ここでは、効率的に調査・準備を進めるためのポイントを紹介します。
まず、高校1年生または2年生の段階から、子どもの通う高校の進路指導の先生に相談することをおすすめします。学校には様々な奨学金や支援制度の情報が集まっているため、子どもの成績や家庭状況に応じたアドバイスをもらえることが多いです。
また、同時に居住地域の自治体(市区町村の教育委員会や福祉課)にも問い合わせ、地域独自の支援制度がないか確認しておくとよいでしょう。
次に、インターネットや書籍を活用して、より広範囲の情報を集めます。日本学生支援機構(JASSO)のウェブサイトでは、奨学金に関する詳細な情報が得られます。
また、「ひとり親家庭 大学進学」「シングルマザー 教育費支援」などのキーワードで検索すると、様々な情報サイトや体験談にアクセスできます。
調査で得た情報をもとに、「利用できそうな支援制度リスト」を作成し、それぞれの申請時期や必要書類、条件などを整理しておくと便利です。特に、高校3年生の4月から7月にかけては多くの奨学金の申請時期となるため、この時期に向けて準備をしておくことが重要です。
準備すべき主な書類としては、「課税証明書」「源泉徴収票」「住民票」「戸籍謄本」「ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当証書など)」などがあります。
これらの書類は取得に時間がかかることもあるため、事前に用意しておくとスムーズです。また、奨学金の申請では子どもの学業成績も考慮されることが多いため、日頃から学習習慣を身につけ、一定以上の成績を維持することも大切です。
さらに、大学側の支援制度も忘れずにチェックしましょう。多くの大学では独自の授業料減免制度や奨学金制度を設けています。
特に、ひとり親家庭や経済的に困難な家庭向けの特別枠を設けている大学もあります。志望校が決まったら、その大学のウェブサイトや入試課に問い合わせて情報を集めておくとよいでしょう。
申請スケジュールの立て方
大学進学に向けた支援制度の申請は、それぞれ時期が異なるため、計画的に進めることが大切です。効果的な申請スケジュールを立てるには、まず「いつまでに何をするか」を明確にしたカレンダーを作成すると良いでしょう。
具体的には、高校2年生の秋頃から準備を始め、高校3年生の4〜7月に多くの奨学金申請を行い、大学合格後に最終的な資金計画を固めるという流れが一般的です。
例えば、高校2年秋には情報収集と成績向上への取り組みを開始し、高校3年の春には必要書類(課税証明書や戸籍謄本など)の準備を始めます。
6〜7月はJASSOや地方自治体の奨学金申請のピークとなるため、この時期に向けて準備を進めることが重要です。また、高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金と授業料減免)の申請も同じ時期に行うことが多いです。
志望校が決まってきたら、各大学の独自奨学金や授業料減免制度の申請時期も確認しておきましょう。大学合格後には、入学時に必要な費用の準備や、国の教育ローンなどの申請を行います。
こうしたスケジュールを親子で共有し、期限に遅れないよう協力して進めていくことが成功の鍵となります。忘れずに、各申請の期限を複数の場所(カレンダーやスマホのリマインダーなど)に記録しておくと安心です。
進学先で学ぶ内容と将来設計の話し合い
大学進学を考える際、「どうやって費用を工面するか」という経済的な側面だけでなく、「なぜその大学・学部で学びたいのか」「将来どのようなキャリアを目指しているのか」という内容的な側面についても、親子で話し合うことが大切です。
特にシングルマザー家庭では、限られた教育資金をどこに投資するかという判断が重要になるため、子どもの本当の興味や適性、将来のビジョンを理解することが不可欠です。
まず、子どもがどのような分野に興味があるのか、どのような職業に就きたいと考えているのかを、オープンな対話を通じて探っていきましょう。
「あなたが本当に学びたいことは何?」「将来どんな仕事をしていると想像する?」といった質問から始め、子どもの考えに耳を傾けることが大切です。
子どもの回答が漠然としている場合は、一緒に適性検査を受けてみたり、興味がある分野の職業人のインタビュー記事や書籍を読んでみたりするのも良いでしょう。
次に、子どもの興味や適性に合った学部・学科を探していきます。大学のオープンキャンパスに親子で参加したり、大学のパンフレットやウェブサイトを一緒に見たりしながら、具体的にどのようなことが学べるのかを調べましょう。
単に「偏差値が自分に合っている」とか「就職に有利そう」という理由だけでなく、本当に学びたい内容があるかどうかが重要です。
さらに、その学部を卒業した後のキャリアパスについても考えてみることが大切です。「この学部を卒業するとどんな職業に就ける可能性があるのか」「その職業の就職状況や年収はどうなのか」
といった現実的な側面も、将来の経済的自立に向けて重要な判断材料になります。特に、奨学金を借りる予定がある場合は、卒業後の返済と収入のバランスも考慮する必要があります。
こうした話し合いを通じて、子どもの夢と現実的な選択肢のバランスを取っていくことが大切です。シングルマザーとして「子どもの好きなようにさせてあげたい」という気持ちと「将来の安定も考えてほしい」という思いの間で葛藤することもあるでしょう。
しかし、オープンな対話を通じて互いの考えを理解し合い、子ども自身が主体的に進路を選択できるよう支援することが、真の親の役割と言えるでしょう。
- 子どもの本当の興味・適性を理解する
- 大学で学ぶ内容と子どもの希望が合致しているか確認
- 卒業後のキャリアパスと経済的自立の見通しを考える
- 奨学金返済を含めた将来の収支バランスを検討
- 親の希望だけでなく、子ども自身の意思を尊重する
まとめ:支援制度をフル活用して子どもの夢をサポート
ここまで、シングルマザー家庭が直面する大学費用の課題から、活用できる様々な支援制度、そして親子で一緒に考える進学プランまで、幅広くご紹介してきました。「シングルマザーだから子どもを大学に行かせるのは難しい」と諦める必要はありません。
確かに経済的な制約はあるかもしれませんが、この記事でご紹介したような支援制度を上手に組み合わせることで、子どもの夢を応援することは十分に可能です。
大切なのは、早めの情報収集と計画的な準備、そして親子のオープンなコミュニケーションです。子どもの将来のために、ぜひこれらの情報を活用して、無理のない大学進学プランを立ててみてください。
最後に、シングルマザーのみなさんへのエールとして、よくある質問にお答えする形でまとめていきましょう。
- シングルマザー家庭では、どのような支援制度が特に利用しやすいですか?
-
シングルマザー家庭では特に「高等教育の修学支援新制度」と「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」が利用しやすい傾向にあります。高等教育の修学支援新制度では、ひとり親家庭は所得基準が優遇されるため、比較的採用されやすく、授業料免除と給付型奨学金を受けられる可能性が高まります。また、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度はシングルマザー専用の支援制度で、低利または無利子で教育資金を借りることができます。さらに、各自治体の奨学金でもひとり親家庭優先枠を設けているケースが多いので、お住まいの地域の制度も必ずチェックしてみてください。
- 奨学金や教育ローンの返済が不安です。子どもと親のどちらが返済すべきでしょうか?
-
返済の負担については、事前に親子でしっかり話し合うことが大切です。一般的な考え方としては、給付型奨学金(返済不要)はもちろん最大限活用し、貸与型奨学金(返済必要)については、「生活費部分は子ども自身が卒業後に返済」「授業料部分は親が負担」といったように役割分担をするケースが多いようです。特に第二種奨学金(有利子)は金額が大きくなりがちなので、本当に必要な金額だけを借りるように計画することも重要です。また、返済計画を立てる際は、卒業後の予想収入と月々の返済額のバランスを考慮し、無理のない計画を立てましょう。将来的な負担を減らすためには、給付型奨学金や授業料免除などの返済不要の支援を最大限活用することがポイントです。
- 子どもの希望する大学が経済的に厳しい場合、どう話し合えばいいですか?
-
子どもの希望と経済的現実のバランスを取ることは難しい問題です。まず大切なのは、経済的な制約を正直に伝えつつも、子どもの夢や希望を否定しないことです。「お金がないからダメ」と一方的に却下するのではなく、「どうしたら実現できるか一緒に考えよう」という姿勢で対話を始めましょう。具体的には、希望の大学の授業料や生活費の総額を計算し、利用できる支援制度を調査した上で、どの程度の資金が不足するかを明確にします。その上で、「国公立大学への変更」「地元大学への進学」「奨学金の活用」「アルバイトとの両立」など、様々な選択肢を子どもと一緒に検討していきます。子どもが自分で選択肢を比較し、納得して決断することが大切です。また、経済的理由で第一志望を諦めざるを得ない場合も、「この選択が将来どんな可能性を開くか」という前向きな視点で話し合うことで、子どもの挫折感を和らげることができるでしょう。

支援制度がこんなにあるなんて!これを読んで、子どもを大学に行かせる希望が見えてきたわ

その気持ち、素敵よ!経済的な壁はあっても、工夫次第で乗り越えられるわ。あなたの子育て、これからも応援しているわね!
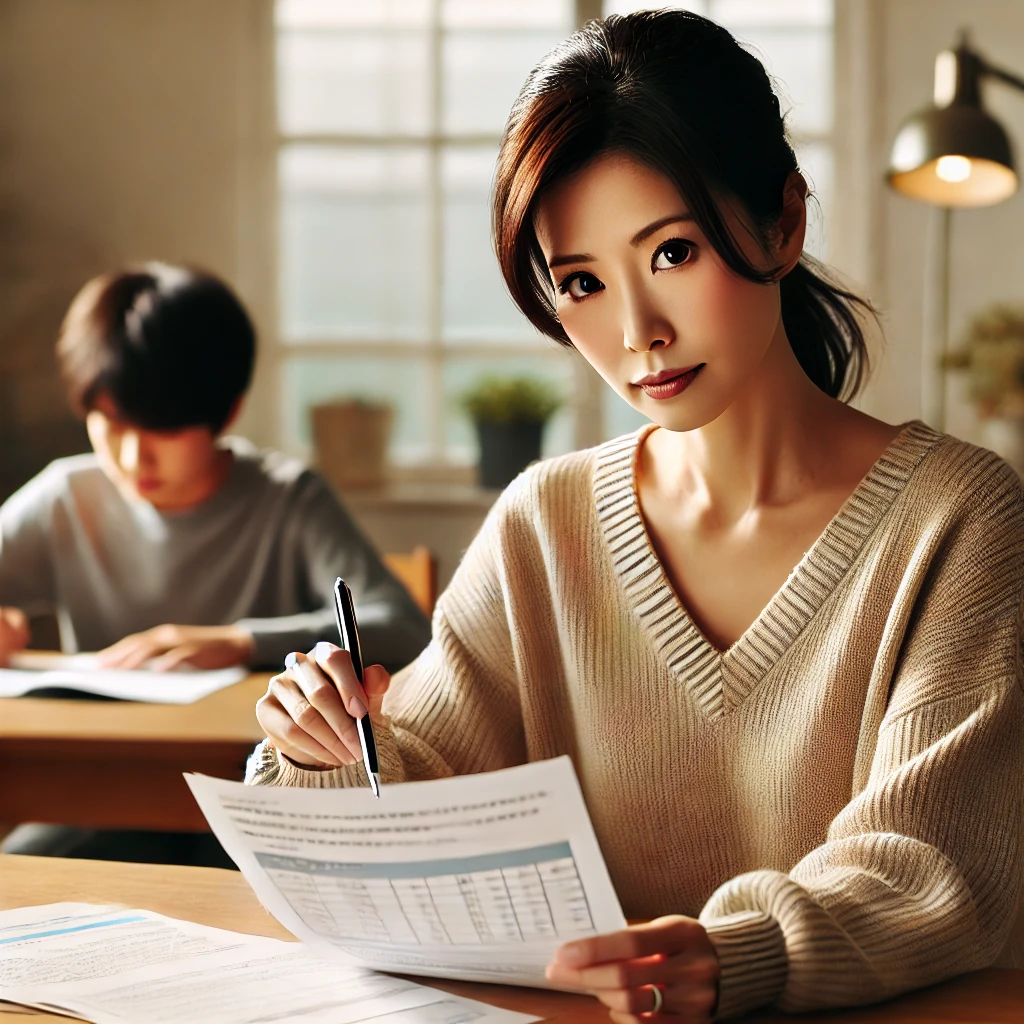






コメント